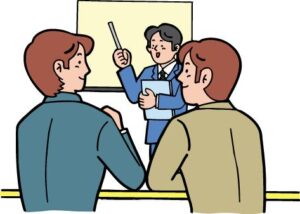改善・改革の着眼点・・共通、共用化
共通・共用化のメリット
共通・共用化を図ることのメリットは大きい。
部品や部材の共通化が図れると、発注単位を大きくできコストダウンが可能になる。
また、部品や部材の点数が少なくできるので大幅な在庫削減も可能になる。
部品・部材が共通化されていれば、色々な部品や部材の品質評価する場合と比較すると、品質評価工数も削減できる。
生産現場では共通・共用化が図られていると切り替えロスの削減のみならず、部品や部材の間違いが減り、製造品質も良くなる。
さらに部品・部材が異なることによるトレーニングも減らすことができる。
また、部品・部材を置くスペースも種類が少ないことからわずかなスペースですむことになり、面積生産性の向上のみならず、物流工数も減らせることになる。
設計の標準化が必要不可欠
しかし、この推進が適切にできていない例は多い。
設計業務は、専門知識が必要なことから、属人化しやすい。
設計者が、共通・共用化を意識せずに、図面を描いてしまうと、どんどん種類は増えていくことになる。
それだけに、この推進を図るには、設計の標準化が必要不可欠だ。
設計の標準化を図ることができれば、設計工数も格段に少なくできる。
共通・共用化のディメリット
ところで、共通・共用化はメリットだけではなく、ディメリットもある。
共用化することで過剰品質になったり、コンパクトにできるのに大きくなったりするなど、コスト高になることもある。
また、共用化することで進化が止まることもある。技術や材料の進化が反映されず、もっとコンパクトにできたり、性能アップが図れたり、コストダウンが図れるにも関わらず、それができないなどだ。
それだけに、定期的な見直しが大切だ。
言い換えると、共通・共用化には、組織として徹底した標準化推進をすることが鍵となるが、それと共に定期的にどのタイミングで見直すかを検討することが大切なのだ。
また、共通・共用化した部品や部材で品質問題があると、数量が多いだけに大規模な品質問題になる。それを防ぐためには、新たに部品や部材、またユニットなどを共通・共用化する場合は、徹底した品質確認が重要だ。
組織として計画的な取り組みを
共通・共用化の効果は大きい。この実現には、組織として共通・共用化を推進する体制を作ることが重要であり、そこに知恵を集めることが大切だ。
また、共通・共用化を実現するには、時間がかかる。
すぐに決めても、一部にはランニングチェンジできるものもあるかもしれないが、多くは、今すでに生産しているものは変更できないことが多い。お客様の了解をいただく必要がある場合もあるし、金型変更が必要になると次期モデルからでないと難しいケースが多いからだ。
時間がかかることを覚悟して、中期の新製品計画を見ながら計画的に推進していくことが大切だ。