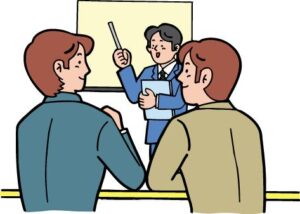海外拠点における従業員の不正と対策
グローバル展開をする上で、注意すべき点の一つが不正問題だ。会計不正や品質不正などがあれば、経営を揺るがすことになるので、どの企業も内部統制に力を入れているが、海外拠点の場合、特に注意が必要なのが、従業員による横領や着服などの不正だ。
不正も権利? 知らぬは日本人だけ
これらの中には、気付かれないまま、長年に渡って従業員が横領していたという例もある。
日本人であれば、横領や着服は許されないというのが当たり前だが、国によっては、権利の一つという感覚のところもある。上司もしていたことで、その役職についた人の特権だったりする。知らぬは、日本人だけという例は多い。
どのような不正が行われているか
それでは、どのような不正が行われているだろうか。
実際に見聞きした例を以下に紹介する。
取引業者へのキックバックの要求
多いのは、取引業者へのキックバックの要求だ。
購買部門で、部材の購入にあたり、業者にキックバック分を上乗せした見積書を提出させて調達価格を決め、業者から差額を受け取るなどだ。
業者側は、注文をもらうことが重要なので、言われるままに対応することが大半。業者が告発しない限り不正は発覚しないので、取引が継続している限り着服できる。企業は高い材料費を継続して支払っているということになる。
このようなことは、購買部門に限らず、事務用品や間接材料の調達でも発生している。
コピー用紙などの事務用品や工場で使用する手袋のようなものは、一人の担当者に補充管理を任せていることが多い。そうなれば、自分で好きなだけ発注できるので、必要量より多く注文して必要量との差額分を懐に入れることができる。すなわち、発注と検収を同一人物が担当すれば、誰も気付くことなく着服できる。
このような着服や横領は、物の調達以外でも発生している。
従業員の送迎バスの業者に、このまま契約を継続したいのであれば、キックバックを支払うように要求していたという例もある。流石に、この事例では業者が告発したことで発覚したが、告発がなければ気付かれなかったという事例だ。
また、事務所を賃貸契約する際に、家賃を水増しした契約にして、実際の家賃との差額を受け取っていた例もある。
また、多いのが、建物の建築や増改築、改造や補修などに伴う工事代金への上乗せだ。これらは金額が大きく、使用部材も多く、工事内容も多方面にわたるので、不正がしやすく、気付かれにくい。
さらに営業担当者が、販売先と結託して販売促進費を決め、自社が支払う販売促進費の一部を販売先から受け取っていたという例もある。
すなわち、支払いが発生する取引は、横領・着服のチャンスであり、業者は金銭がもらえる限り発注者の言いなりになるケースが大半なので、不正が発生しやすいのだ。
不正請求
取引業者が介在せず、単独で不正を行なうケースもある。それが虚偽の経費請求だ。これは、旅費や飲食費などの精算で多く発生する不正だ。うその出張や水増し請求、また、私的な飲食費を請求したりする例だ。中には、私的に購入したものを請求していたという例もある。
さらに悪質な例は、実態のない法人を設立して取引があるかのように装うという例もある。
経理担当による横領
経理部門のように、お金を扱うところは、不正が発生しやすい。
支払いに関するすべての帳票・証憑が経理部門を通ることから、それをコピー・流用することで、偽の帳票や証憑を作成・処理して着服するなどだ。振込であれば気付かれるが、小切手での支払いにすることで発覚を免れていた。
また、経理の例ではないが、労働組合の委員長が組合費を横領していたという例もある。
窃盗
従業員による不正ということでは、窃盗も多い。製品や部材を盗んで売却したり、高価な価格で売却できる計測器などを盗んだ事例もある。
また、スクラップはじめ産業廃棄物については、利権につながっていることもある。
不正は要の人材を失うことに
このような従業員による不正は、横領であり、会計不正につながる。
当然のことながら、不正を発見すると、懲戒処分を行なうことになるが、その対象が「できるキーパーソン」であることは多い。そうなると事業推進の要となる人材を失うことになる。
それだけに、不正をさせない仕組みを作ることが重要だ。
不正が発覚した経緯
ところで、具体的な対策の前に、これらの不正がなぜ発覚したのかということは、対策の参考になるので、いくつかの事例について不正が発覚した経緯を述べておきたい。
キックバックを要求していた事例は、経営責任者が交代したことをきっかけに発覚した。
購買の例では、材料費率の引き下げが必要なことから、「妥当な調達価格かの調査をする」と経営責任者が発言した直後、何人もの購買担当者が退職。退職した購買担当者が担当していた部材を中心に調査するとバックマージンを上乗せした異常に高い価格で調達していたことが判明した。
さらに、新たな購買担当が、見積りを業者に依頼すると、いくらバックマージンの上乗せをした見積りを出せばよいのか聞いてくるなど、バックマージンの上乗せが長年に渡り常態化していたことが判明した。
手袋の例では、コンサルタントが入って5Sの取り組みを推進する中で、職場別の分散管理をやめて集中管理にすることで、ムダな在庫を減らす取り組みをしたところ、実際の使用量に対して、発注量が異常に多いことが発覚。各職場が勝手に必要量を職場に持って行っていたことから全体の総量は誰もわからないことに目をつけ、一担当者が必要量の倍を発注して実際の納品分との差額分を業者から受け取っていたことが判明した。
経理担当による着服の例では、経理責任者が交代したことで、予実管理の徹底が図られ、差異分析をしていく中で数値の異常が判明。調査の結果、偽の帳票や証憑で処理されている費用があることがわかった。
不正をさせない対策
チェックするのが当たり前の体制に
これら発覚の経緯からもわかるように、チェックするのが当たり前という体制を築くことが重要ということだ。
発注も検収もひとりの人物に任せきりにしているといくらでも不正が可能になる。
逆に、発注と検収を別々の人物が担当していれば不正はおきにくい。すなわち、チェックの仕組みを作り、それが当たり前という姿にすることが重要だ。
特に、検収担当にはチェックする責任を明確に示すことで、見逃すと責任が問われるということを意識させることが大切だ。
定期的な異動も重要
経理の担当業務を長期間固定し、会社の預貯金や小口現金をひとりで出金、管理できる体制が放置されていると不正が発生しやすい。
それだけに定期的に異動させることが重要だ。ちなみに、経理部門以外の職場に異動させるのが難しい場合は、経理業務の中で担当替えをするということでもよい。それだけで不正を防ぐことはできる。
日常の管理の仕組みを
日常の管理ができていないことから横領に気付けていないケースは多い。予算と実績の差異を常に把握し、異常があればすぐに確認していると不正は発覚しやすく、しにくくなる。
経理担当による横領も日常の経営管理の仕組みを導入したことで発覚した例だが、手袋などでも使用量の管理ができていれば誰もが気付いたはずだ。
日頃から行なう実棚(実地棚卸)は、会社の資産を守ると共に、不正防止につながる。違算(実際の数量と帳簿数量の差異)原因の把握や、原価の差異分析なども材料費などの誤魔化しを難しくする。
日頃から管理ができる仕組みを作ることで、すぐに問題に気付けるようにすることが大切なのだ。それが不正の防止につながる。
取引先への徹底
不正の裏には、取引先が協力させられているケースが多い。
それだけに、全取引先に対して、「クリーン調達宣言(不正な取引はしない宣言)」を出すことは有効だ。法令・社会規範遵守の姿勢を示し、公正、健全な調達活動を実現すると宣言することで、担当者からのバックマージンなどの要求があった場合は直接連絡してもらうように、連絡窓口を明示することだ。
定期的な監査
さらに、定期的な監査も有効。
ある程度の規模の企業であれば、日本に監査部門を設置している企業は多い。定期的に監査を受けることで管理体制の不備が見つかることは多い。対応が面倒だからというのではなく、積極的に監査をしてもらう姿勢が重要だ。
不正による損失を無くす
不正は、業績を悪化させると共に、発覚すれば能力ある従業員を失うことになる。それだけに、不正をさせない、不正ができない仕組みを構築することが大切。
実際、不正撲滅を徹底推進し、不正ができない仕組みを確立できた拠点は、それだけで利益が向上する。
不正撲滅への取り組みは、健全な資産管理、利益体質の向上につながるということだ。